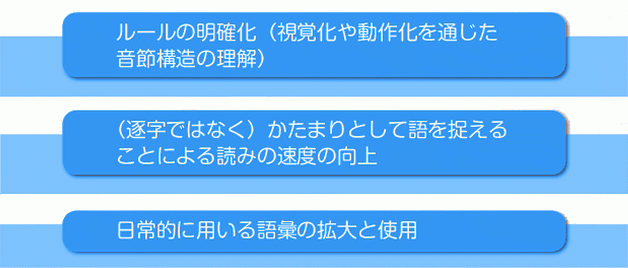タグ:じゃんぷ
K先生のじゃんぷ通信
K先生のじゃんぷ通信
年末が近づいてきました。
じゃんぷは2020年10月の開所から丸1年、おかげさまで利用者様も職員も増えて、去年よりずっとにぎやかな年末となりました。今年はクリスマスツリーに飾るリースを放デイで作ったり、(まだ年内ですが)書き初め企画をしたりと、利用者さんが増えたからこその学習以外の活動も充実してきました。
個別的な支援の中で、アセスメントをしながら読み書きや学習活動の基本から指導をしていきますが、「本当に力がついてきたなぁ」と感じるのは勉強場面だけではありません。数の理解や読み取りの力が伸びたことで、UNOやババ抜き、神経衰弱といったゲーム遊びの楽しさがわかるようになった1年生、おやつを食べながらのちょっとした読み聞かせを楽しみにしている3年生、ホワイトボードにその日の来所メンバーの名前を書いたり数字のクイズを作ったりするようになった読み書き困難のある2年生。
特に低~中学年さんの時期は、遊びや自由なかかわりの中で自信がついてきた力を、生き生きと発揮していきます。遊びの中味や質も、自分達で変えていきます。そんな子供達の姿が見られるのは、勉強も遊びも一緒の時間に行う放課後デイの醍醐味だなと感じます。
「勉強キライ」「今日はちょっとヤル気出えへん」と本音ももらしながら、やって来る子供達。穏やかな放課後の時間の中で、いざ机に向かえば、できそうなところは「ここは自分でできるし、何も言わんといて」と、一生懸命問題に向かう子供たちを見ていると、できない…難しい…という不安や弱音の向こう側に、やっぱり一人でできる!という実感や自尊心を、どの子も求めているのだなと感じます。
来年も、利用するお子さんにとって、穏やかに自分に向かい合い、適切な手助けを受けながら少しがんばれる、…そんな環境の一つになれますように、と思う2021年の年の瀬です。
読み書き障害に対応した学習支援プログラム 【じゃんぷー1】
おかげさまで、当法人の新しい発達障害対応の事業所「じゃんぷ」が10月よりオープンします。「じゃんぷ」の支援コンセプトは「エビデンス・ベースド・プラクティス」つまり「根拠に基づいた支援」です。
あちこちの事業所のホームページをみると、必ず「発達障害」児の様々な支援がうたわれており、その支援も「ソーシャルスキルトレーニング(SST)・学習支援・個別療育・集団療育」とか「TEACCH 感覚統合療法 ソーシャルスキルトレーニング(SST) 学習支援 個別療育 集団療育 預かり支援」「応用行動分析(ABA) 感覚統合療法 言語療法 作業療法 理学療法 遊戯療法 音楽療法 運動療法 ソーシャルスキルトレーニング(SST) 学習支援 個別療育 集団療育 」などなど聞いたような療育が並びます。しかし、これらのどの療法にしても正確なアセスメントを行い個別化しないと取り組めません。それは、利用する子どもたちの凸凹のパターンや凸凹の開き方が違うからです。
「じゃんぷ」でも、幼児にはSIT(Sensory Integration Therapy;感覚統合療法)や小学生にはSSTや学習支援にABA理論に基づいて取り組みますが、こういう個別化した取り組みはアセスメントや評価をしっかりとらないとやっているだけになってしまします。子どもが楽しければいいのならそんなに難しいことは言わなくてもいいのですが、それですらなぜ子どもが楽しいのか、なぜ取り組もうとしないのかという仮説や根拠が必要です。
また、どの放デイにも「学習支援」と掲げられてはいますが、どんな学習支援をするのかは示されていません。「すてっぷ」のように宿題を手伝うことなのか、「じゃんぷ」のように保護者や子どもと契約して特別の個別学習プログラムを実施することなのかで、支援の密度も手法も変わります。
特に発達障害の子どもにみられる、読み書き障害(音韻障害を主とするもの)にどうアプローチするのかは、学校でも知らない先生のほうが多いです。じゃんぷは、認知特性だけでなく音韻意識の流暢性アセスメントをして、この問題に本格的に取り組もうとしています。おそらく、京都府の放デイでは初めての取組になるかと思います。
今回から、「じゃんぷ」の目指す支援について少しづつ紹介していきます。