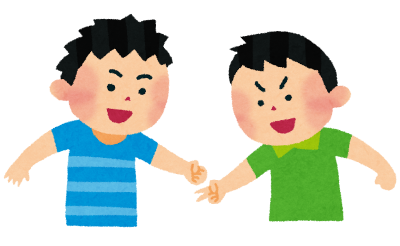タグ:相談
「なんで、僕が勝ったやん」
小学2年生のWくんはじゃんぷに来て半年ほど。家ではお兄ちゃん勝りのお話上手で、じゃんぷでも5、6年生のお兄さんたちとも対等のようにお話を楽しんでいます。一方で外遊びで友だちと遊ぶことや学習といった、じゃんぷで取り組む課題はまだまだあるお子さんです。
先日、Wくんと3年生のXくん、1年生のYくんとでフルーチェ作りをしました。最初に役割分担をし、①粉と牛乳を入れる、②混ぜる、③小さい器に移すの3つの役割を選ぶことになりました。Xくんは先に①を選んだのですが、WくんとYくんは二人とも②の混ぜるがいいと言いました。相談することも課題の1つ、と職員が様子を見ていると、Wくんは「じゃんけんで決めよう」とYくんに提案しました。
じゃんけんで決めることは、よく子どもが提案する方法の1つです。Wくんもよくじゃんけんを提案していて、じゃんぷに来たばかりのまだ1年生だったころ、けん玉を誰が使うかで、Wくんとお兄さんとで相談することになりました。するとWくんは自分から「じゃんけんしよう」と提案したのです。そのときの職員はWくんに「じゃんけんで決めるということは、負けたら後になるということだよ」と確認しました。するとWくんは「分かってるよ」と答え、ジャンケンでけん玉の順番を決めたのでした。
フルーチェの混ぜる役を決めるのにジャンケンを提案したWくん。もちろん負けるということは、混ぜることはできず、③の小さな器に移す役になるということです。「いいよ」と答えたYくんとさっそくジャンケンし、勝ったのはWくん。混ぜる役になるのはWくんのはずでした。ところが職員がYくんに「じゃあYくんが移す役ね」と言うと、Yくんは「しない! 混ぜる!」と言ったのです。「なんで、僕が勝ったやん」とWくんは言いますが、Yくんは首を振り、黙ってしまいました。そこで職員が「Yくんは負けたら混ぜるをしないということが分かってなかったんだね」と尋ねると、Yくんは頷きました。Wくんにとっては当たり前のことが、年下のYくんには分かっていなかったんだと受け止めたWくん。職員から「どうする?」と聞かれると、「譲ってあげる」と混ぜる役をYくんに譲ってあげたのでした。
相談して決める、ということは子どもにとっては難しい課題の1つです。そこには、妥協点を見つける、折り合いをつけるという要素が含まれる場合があり、それがまだできない子どもも少なくありません。Wくんにとっては、ジャンケンで負けた、ということが妥協する理由になるのですが、Yくんにとっては今はまだ、そうではないということです。こういう課題に繰り返しチャレンジしていく中で、妥協点を見つける、折り合いをつけることを少しでも増やしていくことが、相談して決めるために必要な力になっていきます。子ども達が楽しみながら、前向きに取り組めるようにしながらも、そういったコミュニケーション・社会性の力をつけられる支援をしていきたいと思います。
「7,8、10ありがいい!」
小学校に通う子どもたちのグループで今はやっているのがトランプゲームの大富豪。ボードゲームの取り組みの際に、子ども一人ひとりがやりたいゲームを持ち寄って、みんなで遊びや順番を決める機会を作っているのですが、最近は「大富豪がいい!」と声が上がるようになりました。
大富豪はトランプ遊びでポピュラーなものですが、この1年程はすてっぷではあまり取り組んできませんでした。小学校グループの大半が入れ替わったタイミングで、みんなが知っているゲームよりも、誰も知らないゲームを導入から楽しむということを狙ってきたからです。ですが高学年も多くなり、修学旅行など普段はあまり遊ばない学校の友だちと遊ぶ機会も増えてくるだろうと、大富豪を職員から提案することにしました。
さてこの大富豪、ご存じの方も多いと思いますがローカルルールが大変多いゲームです。8切りは大富豪を知っている人ならほとんどが知っているルールだと思いますが、それ以外にも10捨て、7渡しなどのルールもよく導入されます。すてっぷでも、ここまでのルールを最初に導入しました。他には5スキップ、9リバースなど(UNOが元ネタでしょうか)調べれば調べるほどローカルルールが出てきます。ただ子どもたちには「大事なのはどのローカルルールを採用するか事前に相談して決めること」を伝えています。みんなが知っている遊びだからこそ、普段は遊ばない友だちとはすれ違いが起きる可能性があります。なのですてっぷで取り組むときも、始める前に「どのルールありにする?」と子ども同士で相談する機会を作っています。
先日も職員から子どもたちに提起したところ、「7、8、10ありがいい!」「7って何?」「なんでもいいから1枚次の人に渡す」「それ分からんからなしがいい」と次々と意見を出し合うことができました。まだ相談して決めることは難しいので職員が支援に入っています。この日は8切り、10捨てがありのルールで遊び、10捨てを駆使した子が見事1位になりました。ところで大富豪で有名なルールの革命は?というと、2枚出しならまだしも、3枚出し、4枚出しは経験が少なくてわからない!という子が多く、さらに4枚出しなら強さが入れ替わるよと言うとさらに??となるようです。まだまだすてっぷで経験を積む必要がありますが、普段は遊ばない友だちから「大富豪しよう!」と誘われたら、「いいよ! どのルールありにする?」と応えられるよう、今から少しずつ取り組んでいきたいと思います。
イライラした時の対処法
支援学校から帰ってきた高等部生のNくんが職員に声をかけました。「もんもんと(イライラ)していることがあるんだけど」。実はこの日の前日、学校で嫌なことを言われたそうです。中学部の時も嫌なことを言われたことを職員に相談していたNくん。当時のことを思い出したようで、「(中学部のときの)○○さんといっしょかな」と尋ねてきました。職員は気持ちを受け止めながらも、「今日の担当の先生(すてっぷ職員)は誰かな」とNくんと一緒に確認。この日のNくんの担当職員はOさんでした。Oさんは「あとで話を聞く時間を取ります。相談したいことをノートに書いてみる?」とNくんに伝えました。Nくんは「わかった」と答え、ノートに伝えたいことをまとめ始めました。
後日このことを共有した別の職員はNくんの成長に驚きました。昔のNくんはイライラしたことがあっても、素直に相談することは難しかったのです。でも自分の気持ちに気づいてほしいと友だちや職員にアピールするために、ものに当たるなどの不適切行動につながってしまいがちでした。そのNくんが落ちついて相談があることを伝え、職員を待ってから話すことができたのです。さらに驚いたのがノートのことでした。
実はNくん、この数週間ほど前から自分のノートを持ち、自分で記録を書き始めました。きっかけはお母さんが「何があったか忘れないように書いてみたら」とアドバイスしてくれたからだそうです。そこには、自分のできごとや大人からのアドバイス、そして次はこうしようと思っていることなどが、きれいに書かれています。それも時系列がしっかりと整理されて、他の人から見ても分かりやすくなっています。
ノートに話したいことを書き終えたNくん。Oさんの手が空いたのを見計らって、「今、話していいですか?」と尋ねました。Oさんは「いいよ」と答え、Nくんといっしょに机につきました。Nくんは手帳を開き、書いた文字を指で押さえながら、何があったかを話してくれました。自分で書いて整理してから職員に相談できたNくん。本当に素晴らしい成長を見せてくれました。